4月が誕生日の音楽家にはラフマニノフ、團伊玖磨、ヘンデル、フジコ・ヘミングなどがおられます。
それぞれにその方唯一の音楽を表現してこられました
それでは、それぞれの音楽家達について、その生涯の一端を覗いてみましょう。
4月1日~10日 ラフマニノフやカラヤンなど

4月1日はラフマニノフの誕生日
4月1日はセルゲイ・ラフマニノフの誕生日です。
ラフマニノフは4月1日、ロシアで生まれました。(ユリウス暦では3月20日)
ラフマニノフは裕福な貴族の家系に生まれましたが、彼が9歳の時に一家は破産してしまいます。
幼い頃から楽才を示していたラフマニノフは奨学金でペテルブルク音楽院に入学しますが、姉の死で学業に身が入らなくなり落第をしてしまいました。
その後、モスクワ音楽院に転校し、ピアニスト、ニコライ・ズヴェーレフの家に寄宿してピアノを学ぶことになり、そこでチャイコフスキーと出会います。
チャイコフスキーはラフマニノフの才能を認め、目をかけるようになりました。
そしてピアノ科と作曲科を首席で卒業しますが、卒業制作として書いたオペラ「アレコ」はチャイコフスキーから絶賛されました。
しかし卒業後作曲し、グラズノフの指揮で初演された「交響曲 第1番」が失敗し、彼はショックでノイローゼになりますが、それを克服して作った「ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調」彼の作曲家としての名前をゆるぎないものにしました。
それでは、「ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調」を角野隼斗さんと日本フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。
4月2日はフランツ・ラハナーの誕生日
4月2日はフランツ・ラハナーの誕生日です。
フランツ・ラハナーは1803年4月2日、ドイツで生まれました。
シューベルトの親友でエンゲルベルト・フンパーディンクの師として知られています。
シューベルトの「幻想曲 ヘ短調」はシューベルトとフランツ・ラハナーとの連弾で初演されたそうです。
彼には兄弟姉妹がたくさんいて、弟のイグナツとヴィンツェンツは彼と同じくプロの指揮者や作曲家だったので、ラハナー3兄弟と言われました。
彼はケルントナートーア劇場楽長やミュンヘン宮廷劇場総監督など楽壇の重鎮として活躍し、作曲家としてオペラ、8曲の交響曲、室内楽曲などの多数の作品を残しました。
それでは、「フルート協奏曲 ニ短調」をお聴きください。
4月3日は八木澤教司の誕生日
4月3日は八木澤教司さんのお誕生日です。
八木澤教司さんは1975年4月3日、岩手県北上市に生まれました。
八木澤教司さんは人気の吹奏楽曲をたくさん作っておられます。
中学生達は八木澤さんの曲が大好きで、吹奏楽コンクールの自由曲によく登場します。
私が顧問をしていた時も一度、県大会の審査員として来てくださいました。
それから、合唱曲「あすという日が」は東日本大震災の後、私達を励ましましたね。
その前から合唱曲集には載っていて大好きな曲でした。
八木澤教司さんのプロフィールは公式ホームページからご覧ください。
それでは、八木澤教司さんご自身の指揮で、吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」をお聴きください。
4月4日は本居長世の誕生日
4月4日は本居長世の誕生日です。
本居長世は1885(明治18)年、東京下谷に生まれました。
本居長世は国学者本居宣長の6代目の子孫で、「赤い靴」「十五夜お月さん」「七つの子」「青い目の人形」など、たくさんの童謡を作曲して「日本童謡の父」と呼ばれています。
彼は東京音楽学校を首席で卒業しましたが、同期に山田耕筰がいます。
教え子には中山晋平や弘田龍太郎などがいます。
また3人の娘達は素晴らしい歌唱力で本居長世の童謡のほとんどを初演し、その後の童謡歌手達たちの先駆となりました。
1923年に発生した関東大震災後、日系米国人を中心に多くの援助物資が贈られると、そのお礼として日本音楽の演奏旅行が企画され、本居長世と2人の娘達はアメリカ各地で公演を行ったそうです。
それでは、NHK東京児童合唱団による「七つの子」をお聴きください。
4月5日はカラヤンの誕生日
4月5日はカラヤンの誕生日です。
ヘルベルト・フォン・カラヤンは1908年4月5日、ザルツブルクに生まれました。
指揮者カラヤンの名前はクラシックファンでなくても誰もが知っていますよね。
カラヤンは1955年から1989年までベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の終身指揮者・芸術監督を務め、それと同時にウィーン国立歌劇場の総監督やザルツブルク音楽祭の芸術監督なども行いました。
日本での人気も高く「楽壇の帝王」と呼ばれ、1954年の初来日以来、合計11回来日しています。
カラヤンはサントリーホールの建設にも関わり、サントリーホール大ホールはベルリン・フィルをモデルにしていて、ホール前の広場は「カラヤン広場」と名付けられました。
カラヤンはサントリーホールのオープニングを祝う来日公演を病気でキャンセルしましたが、その時、弟子の小澤征爾さんが代役を務めました。
それでは、カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によるベートーヴェンの交響曲第5番第4楽章をお聴きください。
中学校の授業では、よく第5番冒頭の指揮者による聴き比べがあっていました。
4月6日はストラヴィンスキーの誕生日
4月6日はストラヴィンスキーの命日です。
イーゴリ・ストラヴィンスキーは1882年6月17日、ロシアのサンクトペテルブルク近郊で生まれました。
「20世紀最大の作曲家」と讃えられるストラヴィンスキーですが、本格的に音楽を始めたのが20歳という遅咲きの作曲家です。
両親の希望でペテルスブルク大学の法科に進学しますが、そこでリムスキー=コルサコフの息子と出会ったのが縁で、リムスキー=コルサコフの弟子となります。
代表作の一つ「春の祭典」は1913年初演時の大騒動がよく知られていますね。
曲が始まると嘲笑と野次で音楽がほとんど聞こえなくなったそうです。
ストラヴィンスキーは自伝の中で「不愉快極まる示威は次第に高くなり、やがて恐るべき喧騒に発展した」と書いています。
でも現代音楽の演奏会では、こういうことは時々あったのだそうです。
ストラヴィンスキーは1959年、大阪国際フェスティバルの招待により日本を訪問しますが、その時に武満徹の「弦楽のためのレクイエム」のテープを聴き、武満徹を絶賛したのだそうです。
これは武満徹の国内外の評価を一気に高めました。
それでは、バレエ音楽「春の祭典」より第1部「大地の礼賛」をお聴きください。
4月7日は團伊玖磨の誕生日
4月7日は團伊玖磨さんの誕生日です。
團伊玖磨さんは1924年4月7日、東京に生まれました。
童謡や歌劇、交響曲、歌曲、合唱曲など、幅広いジャンルでの作品を残しています。
「ラジオ体操第二」も彼の作曲です。
團伊玖磨さんは12歳の時、既に作曲家を志しておられたようで、息子の将来を案じた父親は、彼を山田耕筰のもとに連れて行き、その道がいかに厳しいかを説得してもらい、あきらめさせようとしました。
ところが、山田耕筰は「やり給え!」と激励したので、彼は作曲家として生きていく決心を固めたのだそうです。(笑)
童謡には「おつかいありさん」「ぞうさん」「やぎさんゆうびん」など、世代を超えて愛される曲の数々が。
私は幼稚園の頃、「やぎさんゆうびん」が大好きでした。
そして「どっちも食べてしまったら、いつまで経ってもお手紙のやり取りが終わらないじゃない!」と悩んだものです(笑)
それから、終戦後平和を祈って作られた「花の街」。
オペラでは、あの「夕鶴」。
合唱曲では「筑後川」があります。
本当にどれも素晴らしい作品です。
團伊玖磨さんは、このように語っておられます。
「誰が作曲したとか作詞したとか、そういうこと、もう忘れて、みんなのものになった時に初めて本当の音楽ですね。」
日本にこんなに素晴らしい音楽家がおられたことに感謝します。
それでは、混声合唱組曲「筑後川」より「河口」をお聴きください。
4月8日はドニゼッティの命日
4月8日はドニゼッティの命日です。
ガエターノ・ドニゼッティは1797年11月29日、イタリアのベルガモに生まれました。
シューベルトと同い年です。
ドニゼッティはロッシーニ、ベッリーニとともにベルカント・オペラの三大巨匠と言われています。
彼は貧しい家庭で育ち慈善音楽院で学びましたが、そこで才能を見出され、後にボローニャ音楽院に入学しました。
その後オペラで頭角を現すようになり、1830年、33歳の時に発表した オペラ「アンナ・ボレーナ」で名声を得ました。
彼は70曲あまりのオペラや教会音楽を作曲し、名声を得て華々しい人生を歩みましたが、頭痛や神経性麻痺に苦しみ、50歳で帰らぬ人となりました。
それでは「愛の妙薬」から「人知れぬ涙」をルイジ・アルヴァの歌でお聴きください。
4月9日は小林研一郎の誕生日
4月9日は「コバケン」こと小林研一郎さんの誕生日です。
小林研一郎さんは1940年4月9日、福島県いわき市に生まれました。
今年で85歳になられます。
小林研一郎さんは高校の体育教師の父親と小学校教師の母親のもとに生まれました。
小学生の頃、ラジオから流れてきたベートーヴェンの交響曲第9番を聴いて感動し、父親の持っていた楽譜を見ながら独学で楽典の勉強を始めたのだそうです。
小林研一郎さんのプロフィールはオフィシャルウェブサイトからご覧ください。
https://maestro-kobaken.com/profile/
今年(2025年)5月29日には、サントリーホールで「コバケンとその仲間たちオーケストラ」20周年記念公演が開催されます。
すごいですね!
コバケンさん、益々ご活躍ください!
それでは、コバケンとその仲間たちオーケストラによるベートーヴェン「交響曲第7番」第4楽章をお聴きください。
4月10日は黛敏郎の命日
4月10日は黛敏郎さんの命日です。
黛敏郎さんは1929年2月20日、神奈川県横浜市に生まれました。
黛敏郎さんは1951年、矢代秋雄さん、別宮貞雄さんと共にパリ国立高等音楽院に入学しますが、「学ぶべきものはない」と1年で退学します。
そして1953年には芥川也寸志さん、團伊玖磨さんと共に「3人の会」を結成し、作曲家としての活動を始めました。
1964年にはテレビ番組「題名のない音楽会」がスタートしますが、黛敏郎さんはその名付け親です。
「題名のない音楽会」は、日頃縁のクラシック音楽を家族で楽しんでもらおうと始まりますが、黛敏郎さんはスタートから33年間、司会を務められました。
ちょうど同じ年に東京オリンピックがありますが、黛敏郎さんは記録映画「東京オリンピック」の音楽監督もされました。
それでは「涅槃交響曲」を聴いてみましょう。
4月11日~20日 ヘンデル、スッペ、すぎやまこういちなど

4月11日はすぎやまこういちの誕生日
4月11日はすぎやまこういちさんの誕生日です。
すぎやまこういちさんはゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズの音楽の作曲家として有名ですね。
ご自身も若い頃からゲームが大好きだったそうです。
すぎやまこういちさんのお生まれは昭和6年で、私の亡き父よりも2歳年下ですが、そんな頃にゲームがあったんですね!
私の父はそんな世界を全く知らなかったと思います。
すぎやまさんは1959年のフジテレビ開局から、フジテレビの社員として多くの名番組を生み出しました。
その中の一つが「ザ・ヒットパレード」です。
ラジオで人気の音楽ヒットランキング番組をテレビ化した初めての番組です。
「ザ・ヒットパレード」のテーマソングもすぎやまこういちさん作曲です。
やがてグループサウンズ(GS)の時代がやって来ますが、「ザ・タイガーズ」命名もすぎやまこういちさんだそうです。
「花の首飾り」など、ザ・タイガースに多くの曲を提供しています。
ガロ の「学生街の喫茶店」もだそうです。
懐かしい!
私が中学生の頃です。
そして1986年からは「ドラゴンクエスト」の作曲家として有名になり、1987年からはオーケストラを率いて「ファミリークラシックコンサート」や「『ドラゴンクエスト』コンサート」などのコンサートを主催し、指揮もされました。
それでは、交響組曲「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」をすぎやまこういちさんの指揮でお聴きください。
4月12日はゲンリフ・ネイガウスの誕生日
4月12日はゲンリフ・ネイガウスの誕生日です。
ゲンリフ・ネイガウスは1888年4月12日、ウクライナに生まれました。
ピアニストで音楽教師のゲンリフ・ネイガウスはスタニスラフ・ブーニンの祖父にあたります。
彼はピアノ教師であった両親からピアノの手ほどきを受けますが、母方の親戚カロル・シマノフスキから大きな影響を受けます。
11歳でショパンの作品を演奏してデビュー、1902年には11歳のヴァイオリニスト、ミッシャ・エルマンと共演してリサイタルを開きました。
その後、教育への情熱から演奏活動を止め、1922年にモスクワ音楽院教授となり、1935年から1937年まで院長も務めました。
そして、エミール・ギレリスやスヴャトスラフ・リヒテルなど多くの優秀なピアニストを育てました。
彼の著書「The Art of Piano Playing(ピアノ奏法論)」はピアノ演奏法の代表的な書籍として有名です。
こちらは「ドキュメンタリー『偉大なる師 ゲンリヒ・ネイガウス』」に日本語字幕をつけたものです。
ぜひご覧ください。
この中で流れた下の字幕が大変印象的でした。
「彼による自身の評価はこうだ『ピアニストとしては・・・平凡、音楽家としては・・・良い、芸術家としては・・・大変結構、人間としては・・・良い傾向にある』。」
4月13日はビル・コンティの誕生日
4月13日はビル・コンティの誕生日です。
ビル・コンティは1942年4月13日、アメリカのロードアイランド州に生まれました。
今年、83歳になられます。
あの、シルヴェスタ・スタローン主演の映画「ロッキー」のテーマ曲の作曲者です。
幼いころから父にピアノを学び ルイジアナ州立大学で作曲を専攻しました。
1971年から映画音楽の作曲を担当するようになり、「ロッキー」は4作目です。
ビル・コンティさんはシルヴェスタ・スタローン出演の作品を多く手がけています。
1998年と1999年はアカデミー授賞式の音楽監督もされました。
現在も現役で活動されています。
それでは、「ロッキーのテーマ」をフルオーケストラでお聴きください。
4月14日はヘンデルの命日
4月14日はヘンデルの命日です。
ヘンデルは1685年2月23日、ドイツのハレに生まれました。
バッハと同じ年です。
ヘンデルは幼い時から音楽の才能を示しましたが、父親は彼が音楽をするのを反対していました。
しかしヘンデルは父に内緒で、夜中にクラヴィコードの練習をして腕を上げていたのだそうです。
父親の死後、ハレ大学に進み、音楽と勉学に励みます。
ヘンデルはハンブルクでオペラ作曲家として活動した後、イタリアで修行し、イタリア・オペラの様式を学びました。
その後ロンドンに渡り、当時のイギリス王室のために、オペラやオラトリオ、組曲「水上の音楽」「王宮の花火の音楽」など数多くの作品を作曲しました。
オラトリオ「メサイア」の「ハレルヤ・コーラス」は今でも世界中で演奏されています。
私も大学の卒業演奏会で歌い、興奮の渦に浸りました。
今回は「水上の音楽」より「アラ・ホーンパイプ」をお聴きください。
明るい響きが幸せな気持ちにさせますね。
4月15日はファッシュの誕生日
4月15日はファッシュの誕生日です。
ヨハン・フリードリヒ・ファッシュは1688年4月15日、ドイツのブッテルシュテットに生まれました。
彼は幼い頃から音楽家として活躍し、ドイツ全土で演奏旅行を行い、1714年にバイロイトの宮廷楽団にヴァイオリン奏者として入団、1722年にはツェルプストの宮廷楽長に就任し、亡くなるまでその地位にありました。
彼の作品は存命中には全く出版されることなく、4つの歌劇はそのまま散逸してしまったそうです。
しかし、同時代の人々から高い評価を受けており、バッハはファッシュの多くの作品を写譜し、また編曲しているのだとか。
ツェルプスト/アンハルト市では国際ファッシュ・フェスティバルが行われており、今年2025年6月19日~22日には彼の死後225年を記念し、彼が活躍した場所を巡るイベントが開催されるそうです。
それでは、「トランペット協奏曲 ニ長調」第3楽章をお聴きください。
4月16日はヘンリー・マンシーニの誕生日
4月16日はヘンリー・マンシーニの誕生日です。
ヘンリー・マンシーニは1924年4月16日、アメリカ オハイオ州に生まれました。
映画「ティファニーで朝食を」の主題歌「ムーン・リバー」などの作曲家です。
幼い頃から、フルート奏者の父親にフルートとピッコロを学び、ジュリアード音楽院に進学します。
その後、グレン・ミラー楽団にアレンジャー兼ピアニストとして採用されますが、1952年にユニバーサル映画に入社。
1960年代からは「ティファニーで朝食を」「シャレード」などオードリー・ヘプバーン作品で注目を浴びました。
特に「ティファニーで朝食を」の中でヘプバーンが歌った「ムーン・リバー」は大ヒットしました。
私は、映画「トムとジェリーの大冒険」や「子象の行進」もヘンリー・マンシーニの作品と知ってびっくりしました。
「子象の行進」は確か小学1年生か2年生の音楽の鑑賞教材でしたね。
今日は「子象の行進」を聴いてみましょう。
4月17日はアルトゥル・シュナーベルの誕生日
4月17日はアルトゥル・シュナーベルの誕生日です。
アルトゥル・シュナーベルは1882年4月17日、ポーランドのリプニークに生まれました。
世界で初めて、ベートーヴェンのピアノソナタ全集とピアノ協奏曲全集をレコーディングしたピアニストとして知られています。
幼い頃から「天才少年」として楽才を発揮し、ウィーン音楽院に入学。
8歳でモーツァルトの協奏曲を弾きデビューします。
ブラームスから「将来最も恐るべき天才」と絶賛されたそうです。
その後ベルリンに移住し、ベートーヴェン没後100周年記念演奏会で7夜にわたってピアノソナタを全曲演奏しました。
そして、1932年から1937年にかけて、世界で初めて、ベートーヴェンのピアノソナタとピアノ協奏曲全集をレコーディングしました。
それでは、ベートーヴェンのピアノソナタ第31番をお聴きください。
4月18日はスッペの誕生日
4月18日はスッペの誕生日です。
フランツ・フォン・スッペは1819年4月18日、オーストリアで生まれました。
彼はウィーンで活躍し、30以上のオペレッタとオペラを作り、「ウィンナ・オペレッタの父」とも呼ばれます。
スッペと言えば、小学校の音楽の教科書にも載っていた「軽騎兵」序曲を思い出される方が多いことでしょう。
それから、「ボッカチオ」の中のアリエッタ「恋はやさし野辺の花よ」は、タイトルを見ただけでメロディーが思い浮かぶのではないでしょうか?
日本では浅草オペラで大ヒットした曲です。
それから「詩人と農夫」も有名ですね。
これはカール・エルマーの喜劇のための音楽として作られましたが、スッペの没後、1900年頃にゲオルク・クルーゼがスッペの他の作品と組みあわせてオペレッタ化にしたのだそうです。
それでは、「詩人と農夫」序曲を聴いてみましょう。
4月19日は幸田延の誕生日
4月19日は幸田延(こうだ のぶ)の誕生日です。
幸田延は1870(明治3)年4月19日、東京都に生まれました。
ヴァイオリニストでありピアニスト、作曲家である幸田延はクラシックの分野で日本初の作曲家とされ、妹のヴァイオリニスト安藤幸(あんどう こう)とともに、日本における本格的音楽家の草分けとされています。
幸田露伴の妹であり、瀧廉太郎や山田耕筰は彼女の弟子です。
彼女が東京女子師範学校附属小学校に通っていた頃、音楽取調掛(現在の東京藝術大学)のメーソンが合唱指導に来ます。
その時、彼女はメーソンに才能を見出され、メーソンにピアノを師事するようになりました。
そして12歳で音楽取調掛に進み、卒業後は母校で教えていましたが、1889年に日本初の音楽留学生に選ばれ、アメリカとウィーンで学びました。
幸田延はウィーン音楽院時代に「ヴァイオリンソナタ第1番 変ホ長調」を作曲し、帰国後の1897年に東京音楽学校学友会演奏会で演奏されました。
これが日本人による初のクラシック音楽作品となります。
帰国後は東京音楽学校(現在の東京藝術大学)教授となり、滝廉太郎などを育てました。
順風満帆に見える幸田延の生涯ですが、実は激しいバッシングとフェイクニュースのゆえに東京音楽学校を辞めてヨーロッパに旅立ちました。
まだ、幸田延39歳の時のことです。
それでは、「ヴァイオリンソナタ第1番 変ホ長調」をお聴きください。
4月20日はニコライ・ミャスコフスキーの誕生日
4月20日はニコライ・ミャスコフスキーの誕生日です。
ニコライ・ミャスコフスキーは1881年4月20日、ロシアで生まれました。
彼は軍人の家庭に生まれ、軍隊に入った後、25歳でサンクトペテルブルク音楽院に入学します。
そこでプロコフィエフと出会い、2人は生涯に渡る親友となりました。
音楽院卒業後は第1次世界大戦に従軍しストレス障害に陥りましたが、その回復期に2つの交響曲を作りました。
その後は30年余り、モスクワ音楽院で作曲を教え、ハチャトゥリアンやカバレフスキーなど多くの弟子を育てました。
彼は生涯に27の交響曲、13の弦楽四重奏曲など多くの曲を残しました。
こちらは「交響曲第1番 ヘ短調」第2楽章です。
4月21日~30日 フジコ・ヘミング、プロコフィエフなど

4月21日はフジコ・ヘミングの命日
4月21日はフジコ・ヘミングさんの命日です。
フジコ・ヘミングさんは1931年12月5日、ドイツのベルリンで生まれました。
彼女はスウェーデン人画家・建築家の父親と日本人ピアニストの母親との間に生まれました。
1歳の時、家族で日本にやってきましたが、父親は日本に馴染めず、彼女が7歳くらいの時にスウェーデンに帰ってしまいました。
幼い時から母親にピアノを習っていましたが、10歳からレオニード・クロイツアーに師事。
クロイツアーは、「フジコはいまに世界中の人々を感激させるピアニストになるだろう。」と絶賛したそうです。
その通りでしたね。
また、今世紀最大の作曲家・指揮者の一人と言われるブルーノ・マデルナに才能を認められ、レナード・バーンスタインなどからの支持もあり、彼女はブルーノ・マデルナの<ソリストとして契約しました。
しかし、リサイタル直前に風邪をこじらせ、聴力を失うという悲劇が彼女を襲います。
フジコ・ヘミングさんは苦しい時代を経て、再びピアニストとして世界で活躍されるようになります。
以前、「知ってるつもり」というテレビ番組でフジコ・ヘミングさんが取り上げられました。
その時、彼女の演奏を聴いた多くの人が涙を流す理由について、彼女のピアノ演奏の周波数が他の人の演奏とは違うという実験結果が説明されました。
私にはよく分かりませんませんが、きっと彼女は神様からの贈り物だったのではないかと思います。
今年は一周忌にあたり、西武渋谷店で『偲ぶ会』 追悼展が開催されました。
https://fuzjko.net/news/20250325
フジコ・ヘミングさん、ありがとうございました✨
天国でも美しい音色を響かせておられることでしょう🌈
こちらは映画「恋するピアニスト フジコ・ヘミング」の中の「ラ・カンパネラ」演奏シーンです。
https://www.youtube.com/watch?v=1jXcvjwfvaY
4月22日は西本智実さんの誕生日
4月22日は世界的指揮者、西本智実さんの誕生日です。
西本智実さんは1970年4月22日、大阪府大阪市に生まれました。
西本智実さんのプロフィールは公式サイトからどうぞ。
https://tomomi-n.com/ja/profile/
私は一度だけ、西本智実さんのコンサートに行ったことがあります。
憧れの西本智実さんを自分の目で見たいという願望が叶い、本当に嬉しかったです。
もう、智実さん、かっこよすぎる!!
指揮台から落ちるのではないかと思うくらいの激しさで、時々足ががに股になるのが本当にかっこいいんです!
私は演奏を聴くのを忘れて智実さんを見続けるというミーハーでした。(汗)
演奏が終わり、ホワイエでサイン会がありましたが、ちょっと低めの小さい声で「ありがとう」と言ってくださって、指揮の時の雄姿とのギャップがまた印象的でした。
西本智実さんはあるインタビューで、この道に進んだきっかけについて以下のように語られています。
私が習い事をしながら、よく親しんでいたものとして「ロシアンバレエ」があげられます。幼いながらに「美の極致」として理解していたように思います。言葉のない表現であるバレエを視覚的に理解するのを最も助け、感覚に訴えかけてくれたのが音楽だったんです。その音楽が指揮者の加減によって訴えかける力が違うということを少しずつ理解するようになって、それに対して疑問を持つようになったのが指揮者に憧れるきっかけでした。
こんなに活躍されている西本智実さんですが、26歳でロシアの国立サンクトペテルブルク音楽院に留学された時は、貧しさと極寒の中で死にそうな体験をしてこられました。
ある時、夜中に電車が来なくて極寒の中を歩いて帰宅中にアイスバーンで転倒し、楽譜も散乱。
起き上がれずに死を覚悟した時、通りがかった男性に起こされ、背中を押されたのだそうです。
その時「頑張って歩きなさい」とエネルギーを注入された気がして帰宅後おいおい泣いたとか。
そんな、たくさんのことが今の西本智実さんを支えているのかと思うと胸がいっぱいになります。
こちらは西本智実さんがアンバサダーを務める「バチカンと日本 100年プロジェクト」の「響け!平和の鐘 プレミアムコンサート」の模様です。
https://youtube.com/watch?v=jVwTDZrn7jE
4月23日はプロコフィエフの誕生日
4月23日はプロコフィエフの誕生日です。(本人は4月23日と信じていましたが、実際は4月27日だそうです。)
20世紀を代表する作曲家の一人、セルゲイ・プロコフィエフは、実際には4月27日、ロシアで生まれました。
「ピーターと狼」は以前、中学1年の鑑賞教材でした。
幼い頃から母にピアノを習い、5歳で「インドのギャロップ」というピアノ曲を作曲しました。
楽譜を書いたのは母親だそうです。
9歳で最初のオペラ「巨人」を作曲します。
13歳でサンクトペルブルク音楽院に入学。
1918年、第一次世界大戦の終結を前に、27歳のプロコフィエフはアメリカへの亡命を決意します。
その途中で彼は日本に立ち寄りましたが、結果的に2ヶ月滞在することになり、東京と横浜でピアノリサイタルを開催しました。
プロコフィエフの日本滞在は西洋の作曲家として初めての日本訪問でした。
彼はアメリカに移住した後、パリを経て、1936年にロシアに帰国しました。
その年に、有名な「ピーターと狼」が作られます。
これは以前、中学1年の鑑賞教材で、生徒達が大好きでした。
こちらはチェコ・フィルハーモニー管弦楽団による「ピーターと狼」です。
4月24日は服部公一の誕生日
4月24日は服部公一さんの誕生日です。
服部公一さんは1933年4月24日、山形県山形市に生まれました。
今年、92歳になられます。
童謡の「マーチング・マーチ」や「アイスクリームの歌」の作曲者として知られています。
服部公一さんは学習院大学文学部4年生の時、NHKのオーディションに合格し、大学を中退してプロの作曲家として活動を始められました。
1963年にはアメリカのミシガン州立大学に留学。
当時アメリカで有名になっておられた小沢征爾さんなどの協力があり、日本音楽の普及に力を尽くされました。
服部公一さんは50歳を過ぎてから故郷山形をはじめ東北6県で合唱コンサートの指揮を続けておられます。
服部さんは東日本大震災の後、「歌おうNIPPON」プロジェクトへの協力を依頼され、混声四部合唱曲「みちのく美(うるわ)し」を作られました。
現在も各地で歌われています。
作詞も服部公一さんで、「きた・ひろし」というのは服部さんの作詞家としてのお名前です。
4月25日はジェームズ=ピアポントの誕生日
4月25日はジェームズ=ピアポントの誕生日です。
ジェームズ=ピアポントは1822年4月25日、マサチューセッツ州のボストンに生まれました。
彼は作曲家であり牧師でした。
世界中で歌われるクリスマスの定番曲「ジングル・ベル」の作曲者です。
この曲はボストンにある自分の教会の感謝祭のために作りました。
もとのタイトルは「One Horse Open Sleigh(1頭立てのそり)」と言います。
冬にそり遊びをする様子が歌われていて、クリスマスのことや宗教的なことばはありません。
ジェームズ=ピアポントは子ども時代をニューハンプシャー州の寄宿学校で過ごしましたが、母親への手紙に雪の中をそりで走ったことを書いているそうです。
「ジングルベル」はその時のことを思い出して書いたのかも知れませんね。
この歌はとても人気になり、クリスマスでも歌われるようになってアメリカ中に広まりました。
そしてタイトルも「ジングルベル」に変わりました。
こちらは「ジングルベル」オーケストラ版です。
4月26日はエルランド・フォン・コックの誕生日
4月26日はエルランド・フォン・コックの誕生日です。
エルランド・フォン・コックは4月26日、スウェーデンのストックホルムに生まれました。
父親のシグルドも作曲家でした。
彼はストックホルム音楽大学を卒業後、フランスとドイツで作曲と指揮を学びました。
1957年にはスウェーデン王立音楽アカデミーのメンバーとなり、1968年にはストックホルム音楽大学の教授となります。
彼は交響曲、管弦楽曲、協奏曲そして映画音楽など広い範囲での作品を残しました。
「北欧カプリッチョ」はダーラナ地方の民謡からインスピレーションを得て作られました。
「トロルの太鼓」を想わせるティンパニとおおらかなメロディーが印象的です。
https://www.youtube.com/watch?v=bfgkZH2l_f8
4月27日はスクリャービンの命日
4月27日はスクリャービンの命日です。
アレクサンドル・スクリャービンは1872年1月6日、モスクワに生まれました。
スクリャービンについてはこちらをご覧ください。
1月6日はスクリャービンの誕生日です。
ドビュッシーやシェーンベルクとともに20世紀現代音楽の先駆者の一人と言われています。
子どもの頃にピアノを始め即興演奏が得意だったスクリャービンは、10歳の時、自ら希望して陸軍兵学校に入学しました。
しかし虚弱体質であることと楽才があることからモスクワ音楽院への通学が許可されました。
その後正式にモスクワ音楽院に転学。
ラフマニノフとは同級生でした。
スクリャービンは手が小さいのに、絶技巧の難曲に挑戦していたため右手首を故障します。
それから左手を特訓し、「左手のための2つの小品」を作曲しました。
それでは、イリーナ・メジューエワのピアノで、「左手のための2つの小品」から第2曲 夜想曲をお聴きください。
4月28日はフェリックス・バーナードの誕生日
4月28日はフェリックス・バーナードの誕生日です。
彼は人気のクリスマスソング「ウィンター・ワンダーランド」の作曲者です。
フェリックス・ウィリアム・バーナードは1897年4月28日、ニューヨークに生まれました。
彼は指揮者、ピアニスト、そしてポピュラー音楽の作曲家でした。
幼い時から父親に音楽を習い、プロのピアニストとして活動しました。
フェリックス・バーナードはレンセラー工科大学で学んだ後、ピアニスト、作曲家として広く活躍し、有名なアーティスト達への楽曲提供で成功を収めました。
「ウィンター・ワンダーランド」は、これまで200人以上のアーティストにより歌われてきました。
日本では1964年にNHK「みんなのうた」で放送されました。
クリスマスが近づくと、テレビコマーシャルや大型スーパーなどでよく流れていますね。
こちらは大阪桐蔭高校吹奏楽部による「ウィンター・ワンダーランド」です。
4月29日はフアン・カバニーリェスの命日
4月29日はフアン・カバニーリェスの命日です。
カバニーリェスは1644年9月6日、スペインのバレンシア近郊に生まれました。
スペイン・バロックの偉大な作曲家とされ、「スペインのバッハ」とも呼ばれています。
彼はバレンシア聖マリア大聖堂の首席オルガニストとして45年間務めました。
その間、鍵盤音楽のための作品をたくさん作りました。
その手稿がバルセロナのカタルーニャ図書館に保管されていて、そのいくつかはカタルーニャ図書館のウェブサイトから無料でダウンロードできるそうです。
こちらはパッサカリアです。
https://www.youtube.com/watch?v=T5B1lMtU2jQ
4月30日はヘンリー・ローリー・ビショップの誕生日
4月30日はヘンリー・ローリー・ビショップの命日です。
ビショップは1786年11月18日、ロンドンで生まれました。
あの「埴生の宿」の作曲者です。
「埴生の宿」はイギリスの民謡かと思っていたら、ビショップのオペラ「ミラノの乙女」の中のアリアなんですね。
1809年に書かれた最初のオペラ「チュルケスの花嫁」は不幸にも上演直後に劇場が火事になり、楽譜も灰となったそうです。
その後、コヴェント・ガーデン王立歌劇場の専属作曲家になり、多くのオペラやカンタータなどを作曲しましたが、残念ながら現在ではほとんどが忘れ去られています。
1813年にロンドン・フィルハーモニック協会(現在のロイヤル・フィルハーモニック協会)が結成されると、彼は総裁の一人に選ばれ、以降は指揮者や大学教授としても活躍しました。
1842年には音楽家として初めてナイトを叙勲されました。
「埴生の宿」の原曲「Home! Sweet Home!」は1823年に作られたオペラ「ミラノの乙女」の導入部のアリア>です。
https://www.youtube.com/watch?v=izmsa6D4mxw







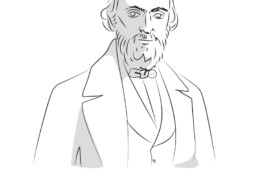

この記事へのコメントはありません。