3月が誕生日の音楽家にはショパンやヴィヴァルディ、ラヴェル、J.S.バッハなどがいます。
また3月が命日の音楽家にはベートーヴェンが!
誰もが知っている有名な方達ですね。
それでは、3月が誕生日や命日の音楽家の生涯に触れてみましょう。
3月1日~10日 ショパンやヴィヴァルディ、ラヴェルなど

3月1日はショパンの誕生日
3月1日はショパンの誕生日です。(誕生日については諸説があるようですが)
フレデリック・ショパンは1810年3月1日、ワルシャワに生まれました。
地上に生きたのは39年間という本当に短い時間でしたが、200年以上経った今もその作品は世界中の人達に愛されていますね♡
その作曲のほとんどをピアノ独奏曲が占めているので、「ピアノの詩人」と呼ばれています。
ショパンの父親はフルートとヴァイオリンを演奏し、母親はピアノを弾き、指導もしていました。
豊かな音楽のある中で育ったショパンは7歳で「ポロネーズ第11番ト短調」を作曲、出版したと言われています。
「ポロネーズ」というのはポーランドの村人たちの踊りの音楽です。
「英雄ポロネーズ」と言われる「ポロネーズ第6番」は32歳の時の作品です。
それから7年後の1849年10月17日、ショパンは39歳という短い生涯を閉じました。
今日は、 亀井聖矢さんが10歳の時の「英雄ポロネーズ」を聴いてみましょう。
3月2日はスメタナの誕生日
3月2日はスメタナの誕生日です。
「チェコ国民楽派の父」と呼ばれるベドルジハ・スメタナは1824年3月2日、チェコに生まれました。
彼は早くから音楽の才能を発揮し、10代の終わりからプラハでピアノと作曲の勉強を続けました。
当時、チェコではオーストリアの支配から抜け出し自国の文化を守ろうとする運動が起きていて、スメタナもそれに共鳴し、祖国への愛情と民族的誇りが込められた作品を作りました。
しかし50歳を過ぎた頃から耳の病気が悪化し、聴覚を失っていきます。
連作交響詩「わが祖国」は50歳だった1874年から1879年にかけて作曲されました。
全6曲の初演は1882年で大成功でしたが、すでに聴覚を失っていたスメタナは聴くことができませんでした。
「わが祖国」は今もスメタナの命日に開催される音楽祭「プラハの春」の初日に必ず全曲が演奏されます。
それでは、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で「わが祖国」より「ヴルタヴァ」(モルダウ)をお聴きください。
3月3日はヘンリー・ウッドの誕生日
3月3日はヘンリー・ウッドの誕生日です。
指揮者、ヘンリー・ウッドは1869年3月3日、ロンドンに生まれました。
彼は敬虔で音楽好きの両親のもとで育ち、ヴァイオリン、ピアノ、オルガンを学びました。
そして14歳でオルガンのソロリサイタルを開くまでになりました。
王立音楽アカデミーに進学し、卒業後はいくつかのオペラ座で指揮者を務め、新作オペラの初演などを行いました。
1895年、ロンドンのクイーンズ・ホールで安価なチケットで気取らない雰囲気の「プロムナード・コンサート」が始まりますが、何と26歳のヘンリー・ウッドが指揮者に指名されたのです。
現在「BBCプロムス」として有名なこのコンサートの正式名称は「ヘンリー・ウッド・プロムナード・コンサート」です。
ヘンリー・ウッドは、回を重ねるに従ってレパートリーを拡大し、BBCプロムスを世界的なコンサートにしました。
最初はポピュラーで、演奏も簡単なものでしたが、そのうちにドビュッシーやシュトラウス、マーラーなどの作品が演奏されるようになりました。
普段、王立音楽アカデミーにあるヘンリー・ウッドの胸像は、この期間はステージに飾られるそうです。
現在はロイヤル・アルバート・ホールで開催され、最終夜「Last Night of the Proms」はイギリス各地の公園で同時生中継イベントも開催されています。
ヘンリー・ウッドは、1895年から1944年に75歳で亡くなるまで、2度の大戦下でもこのコンサートを続けました。
イギリス国民に素晴らしい音楽を届け続けたヘンリー・ウッドってすごい人だったのですね!
それでは、2013年にBBCプロムスに招待された辻井伸行さんの「ラ・カンパネラ」をお聴きください。
3月4日はヴィヴァルディの誕生日
3月4日はアントニオ・ヴィヴァルディの誕生日です。
イタリア・バロック音楽を代表する作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディは1678年3月4日、イタリアのヴェネツィアで生まれました。
彼は司祭になりましたが、体調不良を理由にミサを務めることは少なく、在俗司祭としてピエタ慈善院の教師となり、多くの優れた演奏家を育成しました。
ヴィヴァルディはヴァイオリンの名手でもあり、生涯に500曲以上の協奏曲を作曲しました。
またオペラ劇場の運営も行い、忙しい日々の中、オペラや宗教音楽、室内楽作品も手がけました。
最も有名な「四季」(ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」より)の中の「春」は、中学校で最初に出てくる鑑賞教材ではないかと思います。
各楽章にはソネット(短い詩)が付いていて情景が想像しやすく、各楽器の特徴を知るのにも最適な曲です。
それでは、「四季」より「冬」第2楽章で、しばし癒されてください。
3月5日はエイトル・ヴィラ=ロボスの誕生日
3月5日はエイトル・ヴィラ=ロボスの誕生日です。
ブラジルを代表する作曲家で、クラシック音楽とブラジルの民族音楽を融合させた独自の作風で知られています。
彼はバッハの作品を愛しましたが、同時に「ショーロ」や「モーダ」などと言われるブラジルの民族音楽に魅せられました。
そしてブラジル全土を旅し、1,000曲以上の曲を作りました。
当初は強い批判にさらされたこともありますが、その後ブラジルとヨーロッパやアメリカにその魅力は広まっていきました。
彼はこう語っています。
「私はモダンたらんとして不協和音を書くわけではない。まったく違う。私の作品は、これまでの研究や、ブラジルの自然を映し出すために考え至った集大成の壮大な成果だ。」
「私の作品は返事を期待せずに書いた、後世の人々への手紙である。」
エイトル・ヴィラ=ロボスについては、日本ヴィラ=ロボス協会のサイトからご覧ください。
それでは、「ブラジル風バッハ」第1番をお聴きください。
3月6日はオスカー・シュトラウスの誕生日
3月6日はオスカー・シュトラウスの誕生日です。
オスカー・シュトラウスは1870年3月6日、オーストリアに生まれました。
本来、姓は「Strauss」と綴りましたが、有名なヨハン・シュトラウス(Strauss)一家との混同を避けるために最後のsを一つ省き、「Straus」にしたと言われています。
ワルツが全盛だった時代に、彼は劇場音楽の仕事を選び、オペレッタ作曲者として成功しました。
1904年、最初のオペレッタ「愉快なニーベルンゲン」で大成功を収め、その後、約20曲のオペレッタを作り、「オペレッタの父」と言われるオッフェンバックの後継者としての地位を築きました。
また映画音楽やバレエ音楽も書いています。
1939年にナチスがオーストリアを併合すると、ユダヤ系のためパリに逃れますが、戦後はオーストリアに戻り、最期を迎えました。
それでは「チョコレートの兵隊」からヒルデ・ギューデンのソプラノで「来て来て、私の夢の英雄」をお聴きください。
3月7日はラヴェルの誕生日
3月7日はモーリス・ラヴェルの誕生日です。
今年2025年は生誕150周年です🎉
1901年に書かれた「水の戯れ」は彼の個性が確立された作品で、師であるフォーレに献呈されました。
ラヴェルは1900年から5回にわたってローマ大賞に応募しますが、どれも認められず、5回目は予選落ちになります。
これにフォーレや芸術家、市民達が抗議しました。
これが「ラヴェル事件」です。
その結果、音楽院の腐敗が明らかになり、フォーレが院長となって改革を進めました。
今日は「水の戯れ」を辻井伸行さんのピアノでお聴きください。
3月8日はカール・フィリップ・エマヌエル・バッハの誕生日
今日3月8日はカール・フィリップ・エマヌエル・バッハの誕生日です。
J.S.バッハの二男、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハは1714年3月8日、ドイツのヴァイマールに生まれました。
バッハ家の子どもたちの中で最も多くの作品を残し、「ベルリンのバッハ」または「ハンブルクのバッハ」と呼ばれています。
当時は父、J.S.バッハよりも有名だったそうで、バロックから前期古典派への架け橋となった音楽家です。
彼は30年もの間、ベルリン宮廷でフリードリヒ大王に専属楽師として仕え、クラヴィア奏者として名声を築きました。
その後はハンブルクの5教会の音楽監督に就任します。
ハンブルクでは様々な企画をして人々に音楽を提供し、自らの作品の出版を行いました。
エマヌエルは親しく知人、友人を自宅の食事に招くのを喜びとして、その際請われるままに即興演奏を披露しました。
彼は聴く人に感動を与えることを第一の目的として多くの作品を作り、バロックから前期古典派への架け橋となりました。
それでは、「オーボエ協奏曲 変ロ長調」第2楽章をお聴きください。
3月9日はサミュエル・バーバーの誕生日
3月9日はサミュエル・バーバーの誕生日です。
サミュエル・バーバーは1910年3月9日、アメリカのペンシルベニア州に生まれました。
有名な「弦楽のためのアダージョ」の作曲者で、この曲は作曲者の名前をとって「バーバーのアダージョ」とも呼ばれます。
サミュエル・バーバーはカーティス音楽院を最優秀で卒業し、奨学金を得てローマに留学しました。
その時に「弦楽四重奏曲第1番ロ短調」を作曲しますが、その2楽章を後に編曲したものが「弦楽のためのアダージョ」です。
この曲はケネディ大統領の葬儀で使用されてから一躍有名になりました。
その後も葬儀や慰霊祭などでの定番の曲となったことに対して、バーバー自身は憤慨したということですが、この曲がそのだけ美しく人の心を癒す力を持っているということだと思います。
アメリカ同時多発テロから1年後の慰霊祭や東日本大震災後の復興コンサート、「プラトーン」などの映画でも使われました。
それでは「弦楽のためのアダージョ」をお聴きください。
3月10日はサラサーテの誕生日
3月10日はサラサーテの誕生日です。
ヴァイオリニストであり作曲家のパブロ・デ・サラサーテは1844年3月10日、スペインに生まれました。
サラサーテは8歳で公演をし、10歳の時にはスペイン女王イサベル2世の前で演奏しました。
パリ音楽院卒業後は演奏家としての活動を始め、仲良しのサン=サーンスと演奏旅行をしたそうです。
彼はサン=サーンスやラロ、ブルッフなどから曲を献呈され、初演を行っています。
私は中学の音楽の授業で「ツィゴイネルワイゼン」を聴き、その魅力に取り憑かれました。
それでは「ツィゴイネルワイゼン」をHIMARIちゃんの演奏で聴きましょう。
3月11日~20日 ヨハン・シュトラウス1世、服部正など

3月11日はカティア・ラベックの誕生日
3月11日はラベック姉妹のお姉さんの方、カティア・ラベックさんの誕生日です。
カティア・ラベックは1950年3月11日、フランスのバスク地方に生まれました。
カティア・ラベックさんはピアノ・デュオ、ラベック姉妹のお姉さんの方です。
今年で75歳になられますが、50年以上、世界で活躍してこられ、今も現役です。
すごいですね!
妹のマリエル・ラベックさんは73歳です。
ラベック姉妹はパリ国立高等音楽院で学んだ後、ピアノ・デュオとしてベルリン・フィルその他の主要オーケストラと定期的に共演されてきました。
お二人のレパートリーは幅広く、18世紀から現代音楽にまで至ります。
日本ではサントリーウィスキー21のCMに出演されていましたね。
お二人の姿がとってもチャーミングです♡
それではサントリーウィスキー21のCMをご覧ください。
ガーシュインの「巴里のアメリカ人」が使われています。
後半、「猫ふんじゃった」も(笑)
3月12日は関屋敏子の誕生日
3月12日はソプラノ歌手であり作曲家の関屋敏子の誕生日です。
関屋敏子は1904年3月12日、東京に生まれました。
朝ドラ「エール」で、音の音楽学校時代のライバル、夏目千鶴子のモデルになった人です。
関屋敏子は小学3年生の時、学校を見学に訪れた明治天皇の皇后の前で独唱し、その透き通った美声に皇后感嘆されたそうです。
そのことを知った、当時の世界的オペラ歌手、三浦環は彼女を音楽の世界に誘いました。
その後、彼女はイタリアに留学し、スカラ座のオーディションに一発で合格。
次々と主役の座を得ます。
25歳で帰国すると日本初のオペラ「椿姫」でプリマドンナを務め、山田耕筰も大絶賛したそうです。
1934年には自作自演の日本風オペラ「お夏狂乱」が評判を呼びます。
そんな関屋敏子ですが、自作の「野いばら」の楽譜裏表紙に遺書を残し、37歳という短い生涯を閉じました・・・。
それでは「野いばら」をお聴きください。
3月13日は金井喜久子の誕生日
3月13日は金井喜久子の誕生日です。
金井喜久子は沖縄音楽の素晴らしさを世界に発信し続けた作曲家です。
金井喜久子は3月13日、沖縄県宮古郡(現在の宮古島市)で生まれました。
彼女は1933年、東京音楽学校(現在の東京芸術大学)作曲科に女性として初めて入学しました。
1940年、日本人女性として初めて交響曲を作り、日比谷公会堂で自らの指揮で演奏しました。
翌年には沖縄民謡を組み込んだ交響曲「琉球の思い出」を発表します。
1956年、米軍統治下の沖縄を舞台とした「八月十五夜の茶屋」がハリウッドで映画化されますが、その映画音楽を担当したのが金井喜久子で、彼女は日本の作曲家が海外の映画音楽に進出する先駆けとなりました。
1972年の沖縄復帰記念式典では、彼女が作曲した沖縄復帰祝典序曲「飛翔」が演奏されました。
晩年は、母校の後輩達が「ひめゆり学徒隊」として亡くなったことに心を痛め、「ひめゆり平和祈念資料館」の建設に力を尽くします。
修学旅行の引率で何度も訪れた資料館が彼女の努力でできたとは知りませんでした。
2026年には金井喜久子生誕120年を迎えます。
2023年、音楽と沖縄に生涯を捧げた金井喜久子を多くの人に伝えようと、「金井喜久子プロジェクト」が立ち上がり、朗読や演奏会などが行われています。
それでは、沖縄復帰祝典序曲「飛翔(はばたき)」をお聴きください。
3月14日はヨハン・シュトラウス1世の誕生日
3月14日はヨハン・シュトラウス1世の誕生日です。
「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス2世の父親で、「ワルツの父」と呼ばれています。
ヨハン・シュトラウス1世は1804年3月14日、ウィーンで生まれました。
少年の頃、孤児になったヨハン・シュトラウス1世は親戚に引き取られ丁稚奉公をしますが、ある時飛び出してヴァイオリンを学び、流しになります。
15歳でミヒャエル・パーマーの楽団に入り、その後独立して自分の楽団を立ち上げると大人気となり、ヨーロッパ中を演奏旅行して回りました。
1846年、ヨハン・シュトラウス1世は宮廷舞踏会音楽監督に任命されますが、2年後に三月革命が勃発すると革命側に味方する曲を次々と発表しました。
しかし革命派の行為に疑問を持ったヨハン・シュトラウス1世はオーストリア帝国の英雄ヨーゼフ・ラデツキー将軍を讃える「ラデツキー行進曲」を作りました。
この曲のおかげで政府軍の士気は上がり、「ウィーンを革命から救ったのは、ヨハン・シュトラウスである」とまで言われるようになったそうです。
今でもウィーンフィル・ニューイヤーコンサートの最後に演奏されますね。
オケと聴衆が一体となってつくりあげる演奏は素晴らしいですね!
それでは、「ラデッキー行進曲」をウィーンフィルの演奏でお聴きください。
3月15日はエドゥアルト・シュトラウスの誕生日
3月15日はエドゥアルト・シュトラウスの誕生日です。
ちょうど昨日ポストしたヨハン・シュトラウス1世の四男です。(三男が幼い頃に亡くなったので、彼が三男と言われることも)
彼は外交官を目指したのですが、兄のヨハン・シュトラウス2世が半ば強引に彼を音楽の道に引きずり込みました。
1855年、兄ヨハンの率いるシュトラウス楽団でハープ奏者としてデビューし、1861年には指揮者としてデビューします。
1870年からはウィーン宮廷舞踏会の指揮者を務め、シュトラウス楽団を率いて世界各地を回りました。
彼の作品は軽快で明るいものが多く、特にポルカやギャロップの名手として知られています。
それでは「テープは切られた」を聴きましょう。
競馬のファンファーレや運動会の徒歩競争で使われていますね。
3月16日は大島ミチルの誕生日
3月16日は大島ミチルさんの誕生日です。
大島ミチルさんは1961年3月16日、長崎市に生まれました。
国立音楽大学作曲科在学中から作曲家また編曲家としての活動をされていて、交響曲「御誦」を発表されます。
その後、映画「失楽園」「長崎ぶ らぶら節」やテレビドラマ「ショムニ」、朝ドラ「あすか」など多くのヒット作品を手がけ、日本アカデミー優秀音楽賞や毎日映画コンクール音楽賞などを受賞してこられました。
また、吉永小百合さんの原爆の朗読詩「第二楽章」「第二楽章~長崎から」の音楽も手がけ、各地での朗読会にも参加されて、吉永小百合さんとも深い繋がりを持っておられるようです。
私は考えるタイプではなくて、映像を見るとイメージが湧いてくるんです。感性中心というか…とにかくこのドラマだったら“楽しく見てもらいたい”とか、“やさしい気分になって欲しい”とか、そういう事をメインで頭に描いて書く。」と言われています。
「聴いてくれる人達を喜ばせたい」との思いで、素晴らしい音楽を作り続けてこられた大島ミチルさん、すごい方ですね!
そして何と今年度の全日本吹奏楽コンクール課題曲も作られました!
それでは、2025年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品「Rhapsody ~ Eclipse」をお聴きください。
3月17日は服部正さんの誕生日です。
服部正さんは1908年3月17日、東京に生まれました。
服部正さんは音楽学校ではなく慶応大学法学部の出身ですが、マンドリンクラブの指揮者として活躍されました。
その後は作曲家として日本にクラシック音楽を広める役割を果たされました。
でもクラシックだけではなく、「次郎物語」や「素晴らしき日曜日」などの映画音楽や「キンカン」などのCMソングなども作られています。
一番有名なのは、ラジオ体操第1ですね!
服部正さんは2008年8月2日、100歳でこの世を去られました。
今日はピアノ曲「2つの前奏曲」をお聴きください。
3月18日は菅野よう子の誕生日
3月18日は菅野よう子さんの誕生日です。
あの「花は咲く」の作曲者ですね。
菅野よう子さんは1963年3月18日、宮城県仙台市に生まれました。
菅野よう子さんは11歳の時にヤマハ主催による自作自演曲コンクール、ヤマハ・ジュニア・オリジナル・コンサートで川上賞を受賞されました。
1985年にPCゲーム「三國志」の音楽で作曲家デビュー。
その後は映画やドラマ、CM、アニメ、アーティストへの楽曲提供など、様々な世界で活躍されてきました。
CMソングは1000曲以上を手がけ、「CMソングの女王」とも呼ばれています。
こちらに菅野よう子さんへのインタビュー記事が掲載されていますが、とても興味深く読ませていただきました。
その中にこんなことも書いてありました。
日本語(言語)ってすごく解像度が粗いっていうか。例えばこのお茶を「おいしい」と言っても、喉が渇いてるからおいしいのか、出してくれた人に気を遣っておいしいって言ってるのか、わからないですよね。(中略)でも、音楽だったら、おいしいんだけどもうちょっと甘いほうがいいなとか、そういえば昨日も飲んだなとか、もっといっぱい欲しいな……なんていう気分を1秒のなかで表現できる気がするんです。だから私にはむしろ、そのほうが解像度が高いし、とても楽。
それから確か、ご自分の作った曲の楽譜をチェックしながら他の曲を聴くこともできるとおっしゃっていました。
私には信じられない才能です!!
今年2025年3月11日にはNHK「うたコン」で、菅野よう子さんがピアノを弾かれ、出演者全員が「花は咲く」を歌われました。
それでは「花は咲くプロジェクト」を改めてご視聴ください。
3月19日はディヌ・リパッティの誕生日
3月19日は天才ピアニスト、ディヌ・リパッティの誕生日です。
ディヌ・リパッティは1917年3月19日、ルーマニアに生まれました。
リパッティは11歳でブカレスト音楽院に入学。
1933年に行われた第1回ウィーン国際ピアノコンクールで第2位を受賞します。
審査員を務めていたアルフレッド・コルトーは、彼が1位になれなかったことに抗議して審査員を辞任し、リパッティをパリに招いたのだそうです。
1936年、パリで本格的なデビューを飾り、将来を有望視されたリパッティでしたが、不治の病に冒され、33歳という若さで帰らぬ人となります。
死の2ヶ月前、1950年9月16日、ブザンソン音楽祭でのリサイタルが最後の公開演奏となりましたが、その時の録音は後世への宝物として残っています。
それでは、ディヌ・リパッティによるJ・S・バッハの「パルティータ第1番」をお聴きください。
3月20日はヨーゼフ・フランツ・ワーグナーの誕生日
3月20日はヨーゼフ・フランツ・ワーグナーの誕生日です。
ヨーゼフ・フランツ・ワーグナーは1856年3月20日、オーストリアに生まれました。
リヒャルト・ワーグナーやその一族とは関係ないので、区別するためにJ.F. ワーグナーと表記されます。
オーストリアの軍楽隊長であり作曲家です。
マーチ王、スーザと同世代なので「オーストリアのマーチ王」とも呼ばれます。
代表曲「双頭の鷲の旗の下に」は、彼がオーストリア=ハンガリー帝国の軍楽隊長だった時に作った軍隊行進曲です。
「双頭の鷲」というのはオーストリア=ハンガリー二重帝国のシンボルです。
私は小学生の頃、音楽部でこれを合奏したのを覚えています。
出だしがとても印象的で、その時の情景が浮かんできます。
私はオルガンでした。
それでは、カラヤン指揮、ベルリン・フィル・ブラスオルケスターの演奏で「双頭の鷲の旗の下に」をお聴きください。
3月21日~31日 ベートーヴェン、J.S.バッハなど

3月21日はムソルグスキーの誕生日
3月21日はモデスト・ムソルグスキーの誕生日です。
ムソルグスキーは1839年3月21日、ロシアのカレヴォに生まれました。
「ロシア五人組」の一人ですね。
ムソルグスキーは地主階級の家に生まれ、幼い頃から母親にピアノを習いました。
そしてリストの曲を弾けるまでになります。
彼は士官学校に入学しますが、その頃から作曲を始めました。
その後、軍役を退き作曲に専念することにしたのですが、1861年の農奴解放で経済的に苦しくなった家族を支えるために官吏になり、それでも作曲を続けました。
またバラキレフが設立した無料音楽学校を支援しました。
しかし4度の心臓発作に襲われ、42歳という短すぎる人生を閉じることになりました。
代表曲である「展覧会の絵」は友人だった画家、ヴィクトル・ハルトマンの死を悼んで作られたものです。
もともとピアノのための組曲ですが、多くの作曲家が管弦楽に編曲しています。
特にラヴェルの編曲が有名です。
今回は「展覧会の絵」より「キエフ(キーウ)の大門」を仲道郁代さんのピアノ演奏でお聴きください
3月22日は中山晋平の誕生日
3月22日は中山晋平の誕生日です。
中山晋平は1887(明治20)年3月22日、 長野県下高井郡新野村(現在の中野市)に生まれました。
彼は大正から昭和にかけて数多くの愛唱歌や流行歌を生み出した作曲家です。
その数は1,800曲以上にも上ります。
彼の作品は、日本の抒情的なメロディーと西洋音楽の要素が融合した親しみやすい曲調が特徴で「晋平節」と呼ばれています。
北原白秋や野口雨情、西條八十などの詩人たちと共に作り上げた名曲の数々は、今なお歌い継がれていて「日本のフォスター」とも呼ばれます。
代表作には「シャボン玉」「証城寺の狸囃子」「カチューシャの唄」「ゴンドラの唄」「波浮の港」などがあります。
中野市には中山晋平記念館があり、「ゴンドラの唄」の歌碑があるそうです。
それでは、「ゴンドラの唄」をお聴きください。
3月23日はユリウス・ロイプケの誕生日
3月23日はユリウス・ロイプケの誕生日です。
ユリウス・ロイプケは 1834年3月23日、ドイツに生まれました。
父親はオルガン製作者で、ロイプケは幼い頃から音楽の才能を表していました。
ハンス・ビューローは彼の作曲とピアノの才能に接し、彼をリストに紹介しました。
そしてロイプケはリストの愛弟子となりました。
しかしその2年後、結核のため24歳でこの世を去ったのです。
滝廉太郎を思い出しますね。
あまりにも短い生涯でしたが、彼の「ピアノソナタ 変ロ短調」や19世紀のオルガン作品の最高傑作の一つとされる「詩篇94番によるオルガンソナタ ハ短調」などは今でも愛されています。
それでは、「詩篇94番によるオルガンソナタ ハ短調」をお聴きください。
3月24日はグラナドスの命日
3月24日はエンリケ・グラナドスの命日です。
エンリケ・グラナドスは1867年7月27日、スペインに生まれました。
16歳でリセウ高等音楽院のコンクールで首席に。
その後、パリ音楽院に入学するはずでしたが、病気のために入学はできず、その代わりに音楽院の教授から2年間個人レッスンを受けることができました。
1914年にはパリのコンサートホールで自作演奏会を催し、レジオンドヌール勲章を受章します。
グラナドスはピアニストと作曲家として活躍するかたわら、「アカデミア・グラナドス」を設立して後進の教育にも熱意を注ぎました。
またニューヨークでのオペラ「ゴイェスカス」初演が大成功を収めた際、ウィルソン大統領に招かれてホワイトハウスで演奏会を開くことになります。
しかし、そのためにアメリカ滞在を延長したことがグラナドス夫妻に悲劇をもたらしたのです。
夫妻が乗った船がドイツ軍からの魚雷攻撃を受け、2人は海に投げ出されました。
一度は救命ボートに救われたグラナドスですが、海中に沈もうとする妻を見つけ再び海に飛び込み、帰らぬ人となりました・・・。
享年48歳でした。
それでは、歌劇「ゴィエスカス」より間奏曲をお聴きください。
3月25日はバルトーク・ベーラの誕生日
3月25日はバルトーク・ベーラの誕生日です。
バルトーク・ベーラは1881年3月25日、ハンガリーで生まれました。
幼い頃から音楽の才能を発揮したバルトークはウィーン音楽院への入学を許可されますが、ハンガリーの作曲家としての自分を意識すべきだという友人の薦めに従いブダペスト音楽院に入学します。
優秀なピアニストだったバルトークは民謡の研究を始めていたコダーイと出会い、ともにハンガリー各地の民謡の採集を始めました。
そして、ハンガリー民謡の要素を取り入れた独自の作風を確立し、20世紀のクラシック音楽に大きな影響を与えました。
それでは、「管弦楽のための協奏曲」第5楽章をお聴きください。
3月26日はベートーヴェンの命日
3月26日はベートーベンの命日です。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは1770年12月16日頃ドイツのボンに生まれ、1827年3月26日、56歳の生涯を閉じました。
ベートーヴェンがいなかったら、今の音楽は大きく変わっていたかも知れませんね。
私は「ハイリゲンシュタットの遺書」が強く心に残っています。
1802年、ベートーヴェンは難聴の進行と失恋の痛手をかかえてウィーン郊外のハイリゲンシュタットに静養に出かけます。
そこで「ハイリゲンシュタットの遺書」と言われるものが書かれました。
彼はこの中で、「自分は耳が聞こえなくなっている」という今まで誰にも言えなかったことを告白します。
「皆は私のことを人嫌い、頑固者と言うが、私は人と交流するのが大好きなのだ。でも難聴と知られるのが怖くて、人を避けてきたのだ。」と告白します。
「絶望のあまり、自分の命を断とうとしたが、音楽が私を思いとどまらせれくれた。私が望むすべての作品を仕上げるまでこの世を去ることを、私にはできないのだと悟った。」
1808年に交響曲第6番「田園」が完成しました。
ハイリゲンシュタットの森を歩きながら、実際にはほとんど聞こえない小鳥のさえずりや小川のせせらぎがベートーヴェンの頭の中で響き、オーケストレーションがなされていったことを想像すると涙が溢れます。
そしてそれは、その後の人類へのプレゼントだと思いました。
それでは、交響曲第6番「田園」第1楽章をお聴きください。
3月27日はヴァンサン・ダンディの誕生日
3月27日はヴァンサン・ダンディの誕生日です。
ヴァンサン・ダンディは1851年3月27日、フランスのパリに生まれました。
フランス貴族の家系に生まれましたが、幼くして両親を亡くし、祖母に育てられました。
1872年にパリ音楽院に入学し、セザール・フランクの弟子となりました。
後にパリ音楽院でも指導をしましたが、そこでの教育に疑問を持ち、1894年にスコラ・カントルムを創設しました。
ここでは質の高い教育と古楽の復権が行われ、それはパリ音楽院の改革にもつながりました。
それでは、「フランスの山人の歌による交響曲」をお聴きください
3月28日はジェイ・リビングストンの誕生日
3月28日はジェイ・リビングストンの誕生日です。
ジェイ・リビングストンは1915年3月28日、アメリカのペンシルベニア州で生まれました。
彼はペンシルベニア大学でダンスバンドを結成し、そこで生涯の友となるレイ・エバンズと出会います。
そして2人はコンビを組んで多くの名曲を生み出しました。
特に映画音楽で成功を収め、アカデミー賞歌曲賞を3回受賞しました。
その中の一つに私の大好きな「ケ・セラ・セラ」が!
これは、映画「知りすぎていた男」の主題歌です。
主演女優で歌手でもあるドリス・デイが歌いました。
日本では雪村いづみさんやペギー葉山さんが歌い、ヒットしました。
それでは、ドリス・デイによる「ケ・セラ・セラ」を聴いてみましょう。
3月29日はウィリアム・ウォルトンの誕生日
3月29日はウィリアム・ウォルトンの誕生日です。
ウィリアム・ウォルトンは1902年3月29日、イギリスのランカシャー州に生まれました。
ウィリアム・ウォルトンは正式に作曲を学んだ訳ではありませんが、そのイギリス的作風でエルガーの後継者的存在とも言われています。
1922年に「ファサード」で成功し、翌年、ザルツブルクの第1回国際現代音楽祭において弦楽四重奏曲第1番で作曲家デビューを果たしました。
王室のための作品を書く宮廷作曲家でしたが、映画音楽でも知られています。
それでは、戴冠式行進曲「王冠」をお聴きください。
3月30日は石井歓の誕生日
3月30日は石井歓の誕生日です。
石井歓は1921年3月30日、東京に生まれました。
彼は1952年、西ドイツに留学し、ミュンヘン国立音楽大学に入学し、カール・オルフの弟子になります。
1954年に帰国してからは大学の教授や指揮者としても活躍しました。
また全日本合唱連盟の理事長を務め、おかあさんコーラスの産みの親でもあります。
それから石井歓はアイヌの音楽を取り入れた曲を作っています。
アイヌを題材とした曲と言えば伊福部昭を思い浮かべますが、石井歓は伊福部昭からも大きな影響を受けているようです。
石井歓の父親で舞踏家の石井漠の作品は伊福部昭の曲でできていますし、弟で作曲家の石井眞木は伊福部昭の弟子だったそうです。
それでは「シンフォニア・アイヌ」をお聴きください。
3月31日はバッハの誕生日
3月31日はヨハン・ゼバスティアン・バッハの誕生日です。
ヨハン・ゼバスティアン・バッハは1685年3月31日、ドイツのアイゼナハで生まれました。(ユリウス暦では3月21日)
アイゼナハ周辺にはバッハさんがたくさんいて、同姓同名の人も多かったそうです。
それがバッハ史の研究を大変にしています。(汗)
J.S.バッハは「音楽の父」と呼ばれる程に後世に影響を与えた大音楽家ですが、私は大学の和声学の授業で「バッハは学生時代、劣等生だったんだ。」と聞きました。
たぶんその意味は、バッハは和声学の決まり事に従わなかったということなのかなと思います。 和声学にはいろいろとやっちゃいけないことがあって、例えば2つの声部が並行して上がったり下がったりすることとか。
J.S.バッハは当時の枠に収まりきれない音楽家だったのでしょうね。
でも、そのことがその後の音楽に大きな影響を与えました。
私はビートルズのコード進行はバッハと似てるなぁと思っていましたが、バッハの影響はクラシックに限らず、いろんなジャンルの音楽に広がっています。
バッハは、学生時代は決まりを守らない生徒だったかも知れませんが、未来の音楽を創る上では、まさしく「音楽の父」になったのですね。
今日は、彼の作品の中心をなす約200曲の「教会カンタータ」の中から、コラール「主よ、人の望みの喜びよ」をアカデミー室内管弦楽団の演奏でお聴きください。






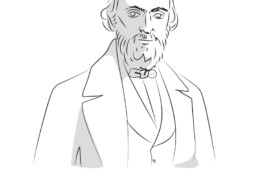


この記事へのコメントはありません。